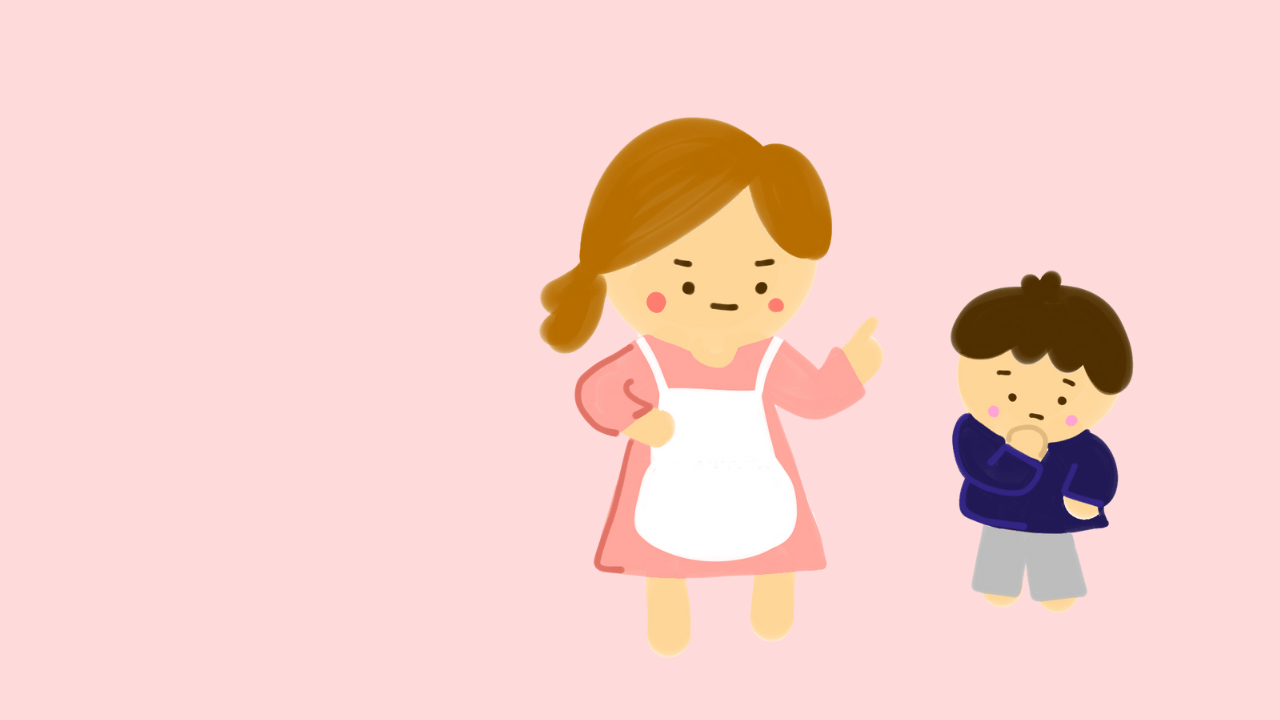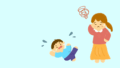こんにちは。高校2年、中学3年の発達障害の男の子ママのひまわりです。
現在、発達障害児の子育て、精神科ナースとしての経験を活かして子育てコーチングの講師をさせていただいてます。
その中で、日常のお子様との関わりが将来、社会に出た際に【指示待ち人間】になってしまうことが見えてきたので、今日は指示待ち人間にならない子育て術を詳しくお伝えしていきます!
なぜ指示待ち人間ができてしまうのか?
日常の中で「アレしなさい」「コレしなさい」って言ってしまうことよくありますよね。
特に朝の忙しい時間は「早く食べなさい」「着替えなさい」「歯磨きしなさい」なんて
よく言っちゃいますよね。
実はこれが指示待ち人間を作ってしまうことに繋がるのです。
想像してみてください。
小さい頃から親に「アレしなさい」「コレしなさい」とやることを指示されていたら、中学生、高校生になっても親の指示がないと動けず、最悪は社会に出てからも上司から1から10まで指示されないと動けない人間に作り上げられてしまうのです。
【指示待ち人間の特徴】
・言われたことしかやらない
・自分で判断することができない
・困った時に誰かに頼ることができない
・新しい環境に適応するのが苦手
・責任を取ることを避けがち
これらの特徴は、すべて幼少期からの「指示される習慣」が作り出してしまうものなのです。
【指示待ち人間にならないための基本原則】
対策は生活の中で子どものことは自分で決めさせる!
実はたったコレだけなんです!
「コレだけでは無理だよ!」って思いますよね。
でも、たったこれだけができてない人が多いんです。
【具体的な声かけの変え方】
- 時間に関する声かけ
❌ 従来の指示**
・ 「早く食べなさい」
・ 「早く着替えなさい」
・ 「早く寝なさい」
⭕ 改善後の声かけ
・ 「何分までに食べ終わる?」
・ 「何分になったら着替え始める?」
・「何時に寝る準備を始める?」
このように自分で時間を決めさせることで、時計を見ながら動くことを覚えます。
もし、時計を見れないお子様だったらキッチンタイマーを使って時間をセットする方法でも大丈夫です。
- 行動の順序に関する声かけ
❌ 従来の指示
・「早く準備しなさい!」
⭕ 改善後の声かけ
・ 「朝の準備は①顔洗い、②ご飯、③着替えどれからする?」
・ 「宿題と明日の準備、どっちから始める?」
子どもからしたら「早く準備しなさい」って言われても、顔を洗うのか、ご飯を食べるのか、着替えるのか、どれからやったらいいか分からない子もいるかもしれません。選択肢を示すことで、自分で優先順位を考える習慣がつきます。
- 学習に関する声かけ
❌ 従来の指示
・ 「宿題やりなさい」
・ 「勉強しなさい」
⭕ 改善後の声かけ
・ 「今日の宿題、いつ頃やる予定?」
・ 「宿題の中で、どれから始める?」
・「集中できる場所はどこがいい?」
【年齢別アプローチ方法】
幼児期(3〜6歳)
・2択から選ばせることから始める
・ 「赤い服と青い服、どっちにする?」
・「おもちゃを片付けてからご飯?ご飯を食べてから片付け?」
小学校低学年(6〜9歳)
・3つの選択肢を提示
・時間を意識させる質問を増やす
・「30分後に出かけるから、それまでにできることは何かな?」
小学校高学年(9〜12歳)
・より複雑な判断をさせる
・ 「今週のスケジュールを見て、いつ宿題をやるのがベストかな?」
・理由も一緒に考えさせる
中学生以上(12歳〜)
・ほぼ自分で計画を立てさせる
・困った時だけサポートする体制に
・「計画通りいかない時はどうする?」という対策も一緒に考える
【実践する際の注意点】
- 忍耐強く見守る
最初は選択肢を伝えたりと大変かもしれませんが、何回も繰り返すことで自ら考えて動くことができるようになります。 - 失敗を責めない
自分で決めたことがうまくいかなくても、「次はどうしたらいいと思う?」と一緒に振り返りの時間を作りましょう。 - 段階的にサポートを減らす
いきなり全部を子どもに任せるのではなく、徐々に自立度を上げていくことが大切です。 - ヘルプの出し方を教える
1人で考えて行動できるようになったら「困った時は声かけてね」って伝えることで、適切にヘルプを出す練習にもなります。
まとめ:将来に向けた投資として
この方法は、目の前の効率よりも、お子さんの将来の自立を重視するアプローチです。
今すぐに効果が見えなくても、継続することで必ず「自分で考えて動ける人」に育っていきます。それは、社会に出た時の大きな武器となり、お子さんの人生を豊かにしてくれることでしょう。
ぜひ今日から実践してみてください!