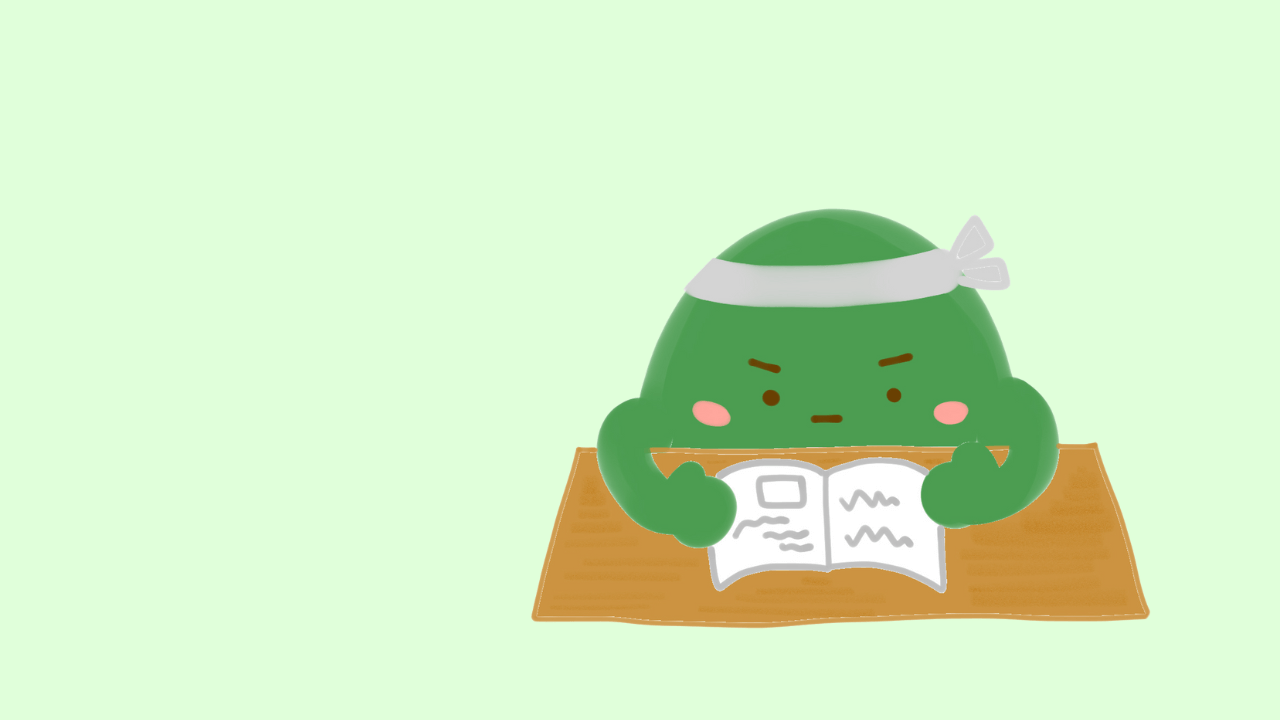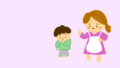受験に耐えられる精神を作る方法
こんにちは。高校2年、中学3年の発達障害の男の子ママのひまわりです。
精神科ナースとして長年勤務し、現在は発達障害児の子育て経験を活かして子育てコーチングの講師をさせていただいています。
我が家の長男は現在高校2年生。2年前に高校受験を経験し、次男は現在中学3年生。今年高校受験を控えてます。今年発達障害のある子どもの受験は、定型発達の子どもとは違った困難さがあります。でも、適切なサポートとメンタルケアで、子どもは驚くほど成長できるのです。
今日は、精神科ナースとしての専門知識と、実際に受験生を育てる親としての経験を踏まえて、「受験に耐えられる精神を作る方法」をお伝えします。
受験に耐えられるために必要な3つのメンタル要素
受験を乗り切るためには、学力だけでなく精神的な強さが不可欠です。精神科での臨床経験から、受験に必要なメンタルは以下の3つの要素で構成されていると考えています。
- 自己肯定感
「自分はやればできる」という基本的な自信です。これがないと、ちょっとした失敗で心が折れてしまいます。 - ストレス対処力(レジリエンス)
プレッシャーや不安と上手に付き合い、立ち直る力です。受験期は長期戦なので、この力が重要になります。 - 継続力
目標に向かって努力し続ける力です。「今日はやりたくない」という日でも、最低限の学習を続けられる力が必要です。
発達障害児特有の受験の困難さ
発達障害のあるお子さんの受験には、独特の難しさがあります。我が家も日々、これらと向き合っています。
ADHDの場合
・長時間の集中が困難
・計画的な学習が苦手
・テストでのケアレスミスが多い
ASDの場合
・環境変化へのストレスが大きい
・予定通りにいかないことへの不安が強い
・試験会場などの不慣れな環境での緊張
・柔軟な思考が求められる問題への対応困難
LDの場合
・特定科目への苦手意識が強い
・努力しても成果が出にくい焦り
・自己肯定感の低下
・読解や計算に人一倍時間がかかる
これらの困難さを理解した上で、適切なサポートを行うことが重要です。
親ができる具体的なメンタルサポート方法
- 小さな成功体験を積み重ねる
NG対応
「なんでこんな簡単な問題も間違えるの?」
「このままじゃ志望校に受からないよ」
OK対応
「今日は30分集中できたね」
「昨日より2問多く解けたじゃない」
発達障害のあるお子さんは、特に失敗体験を引きずりやすい傾向があります。結果だけでなく、プロセスを褒めることで自己肯定感を育てましょう。
- 「できない」を「まだできていない」に変換する
精神科ナースとして学んだ認知行動療法のアプローチです。
NG対応
「この問題、できないんだね」
「数学は苦手だもんね」
OK対応
「この問題は、まだ解き方をマスターしていないだけだね」
「何回か練習すれば、できるようになるよ」
言葉の使い方一つで、子どもの捉え方は大きく変わります。「できない」は固定的ですが、「まだできていない」は成長の余地を示しています。
- 失敗を学びに変える習慣
NG対応
「また間違えたの?ちゃんと見直ししなかったからでしょ」
OK対応
「この間違い、どこで気づけたと思う?」
「次はどうしたら防げるかな?」
失敗を責めるのではなく、一緒に分析する姿勢が大切です。我が家では、結果が出たら「反省会」ではなく「作戦会議」と呼んで、次への対策を一緒に考えています。
- 適切な休息を確保する
発達障害のあるお子さんは、定型発達の子どもよりもエネルギー消耗が激しい傾向があります。
実践していること:
・40分勉強→20分休憩のサイクル
・週に1日は完全休養日を設ける
・好きなことをする時間を確保(ゲーム、音楽など)
・睡眠時間は絶対に削らない
息子はADHDの特性があり、長時間の集中が苦手です。そのため、タイマーを活用して短時間集中を繰り返す方法を取り入れています。最初は10分も集中できませんでしたが、今では40分集中できるようになりました。
- ストレス発散法を一緒に見つける
受験期のストレスは避けられません。大切なのは、健全な発散方法を持つことです。
我が家で効果があった方法:
・軽い運動(ステッパー、ストレッチ)
・好きな音楽を聴く
・短時間のゲーム
・親子での雑談タイム
・深呼吸やマインドフルネス
精神科での経験から、深呼吸は即効性のあるストレス対処法としてお勧めです。「4秒吸って、7秒止めて、8秒かけて吐く」という478呼吸法を、息子にも教えています。
- 栄養バランスを考えた食事の提供
精神科ナースとして、栄養と精神状態の関係性を数多く見てきました。特に受験期は、脳をフル回転させるために適切な栄養が不可欠です。
タンパク質の重要性
なぜタンパク質が必要なのか?
・脳の神経伝達物質(セロトニン、ドーパミンなど)の材料になる
・集中力や記憶力を高める
・精神的な安定をもたらす
・持続的なエネルギー源となる
タンパク質が不足すると、集中力が低下し、イライラしやすくなり、やる気が出なくなります。受験生にとって、これは致命的です。
タンパク質を多く含む食材:
・肉類(鶏むね肉、豚ロース、牛もも肉)
・魚類(鮭、サバ、マグロ)
・卵
・大豆製品(豆腐、納豆、豆乳)
・乳製品(ヨーグルト、チーズ)
我が家では、小さい頃からタンパク質の必要性を伝えていて、冷蔵庫にタンパク質表を貼っているので自分で食べれそうなものをチョイスして食べれるようになりました。
受験生に必要な栄養素
ブドウ糖(炭水化物):
脳の唯一のエネルギー源です。ただし、菓子パンやお菓子ではなく、ご飯やパンなどの複合炭水化物を選びましょう。血糖値の急上昇・急降下を防げます。
ビタミンB群:
神経機能の維持や疲労回復に必要です。豚肉、玄米、納豆、バナナなどに多く含まれます。
オメガ3脂肪酸:
脳の機能維持に重要です。青魚(サバ、イワシ、サンマ)やクルミ、アマニ油に含まれます。
鉄分:
集中力や記憶力に関係します。特に女子は不足しがちなので、レバー、赤身肉、ほうれん草などを意識的に摂りましょう。
避けたい食習慣
カフェインの過剰摂取:
コーヒーやエナジードリンクに頼りすぎると、睡眠の質が低下します。
糖質の過剰摂取:
お菓子やジュースで血糖値が乱高下すると、集中力が続きません。
食事を抜く:
特に朝食を抜くと、午前中の集中力が著しく低下します。
時間がない方でも大丈夫です。サラダチキン、ゆで卵、納豆巻き、豆腐、ヨーグルトなど、タンパク質豊富な食品は他にも沢山あります。手軽に取れる方法を考えてみましょう。
息子は食事内容を変えてから、「午後も集中が続くようになった」「イライラすることが減った」「授業中寝なくなった」と言っています。栄養面からのサポートも、受験を乗り切る重要な要素なのです。
環境を整える重要性
発達障害のあるお子さんにとって、環境は非常に重要です。
学習環境の最適化
チェックポイント:
・気が散るものは視界に入れない
・照明の明るさは適切か
・音の刺激は適切か(静かすぎても集中できない子もいます)
・温度は快適か
・椅子や机の高さは合っているか
息子はある程度の雑音があった方が集中できるタイプなので、カフェの環境音を流しながら勉強しています。
生活リズムの安定化
重要なポイント:
・起床・就寝時刻を一定にする
・3食を決まった時間に食べる
・勉強開始時刻を固定する
発達障害のあるお子さんは、ルーティン化することで安定します。我が家では、朝6時起床、夜11時就寝を徹底しています。
今は朝も一人で起きて、一人で朝ご飯準備してくれてます。
親自身のメンタルケアも忘れずに
子どものメンタルを支えるためには、親自身が安定していることが不可欠です。
親がやってはいけないこと
・過度な期待をかける
「お母さんの夢だった○○大学に行ってほしい」
・他の子と比較する
「○○くんはもう偏差値60超えたんだって」
・自分の不安を子どもにぶつける
「本当に受かるの?お母さん心配で眠れないわ」
親がするといいこと
・子どもを信じる
言葉にしなくても、信頼は伝わります。
・親自身もストレス発散する
親が笑顔でいることが、子どもの安心につながります。
・同じ境遇の親とつながる
一人で抱え込まず、悩みを共有できる仲間を作りましょう。
受験は成長の機会
受験は確かに大変です。特に発達障害のあるお子さんにとっては、定型発達の子ども以上の困難があります。
でも、この経験は必ず子どもを成長させます。
息子は受験勉強を通して、以下のことを学んでいます:
・自分に合った勉強方法
・困難に立ち向かう力
・先の見通しを持つ大切さ
・目標に向かって努力する経験
・親子の信頼関係の重要さ
結果がどうであれ、この経験は必ず将来の糧になります。
受験に耐えられる精神を作る方法まとめ
親の役割は伴走者であり、子どもを引っ張ることでも、後ろから押すことでもありません。
隣を走りながら、時に励まし、時に休息を促す「伴走者」です。
受験に耐えられる精神は、一朝一夕には作れません。でも、日々の小さな積み重ねが、確実に子どもの心を強くしていきます。
完璧な親である必要はありません。時には感情的になってしまうこともあるでしょう。大切なのは、「子どもの味方でいる」という姿勢を持ち続けることです。

あなたとお子さんが、この受験期を通して共に成長できることを願っています。
一緒に頑張りましょう!