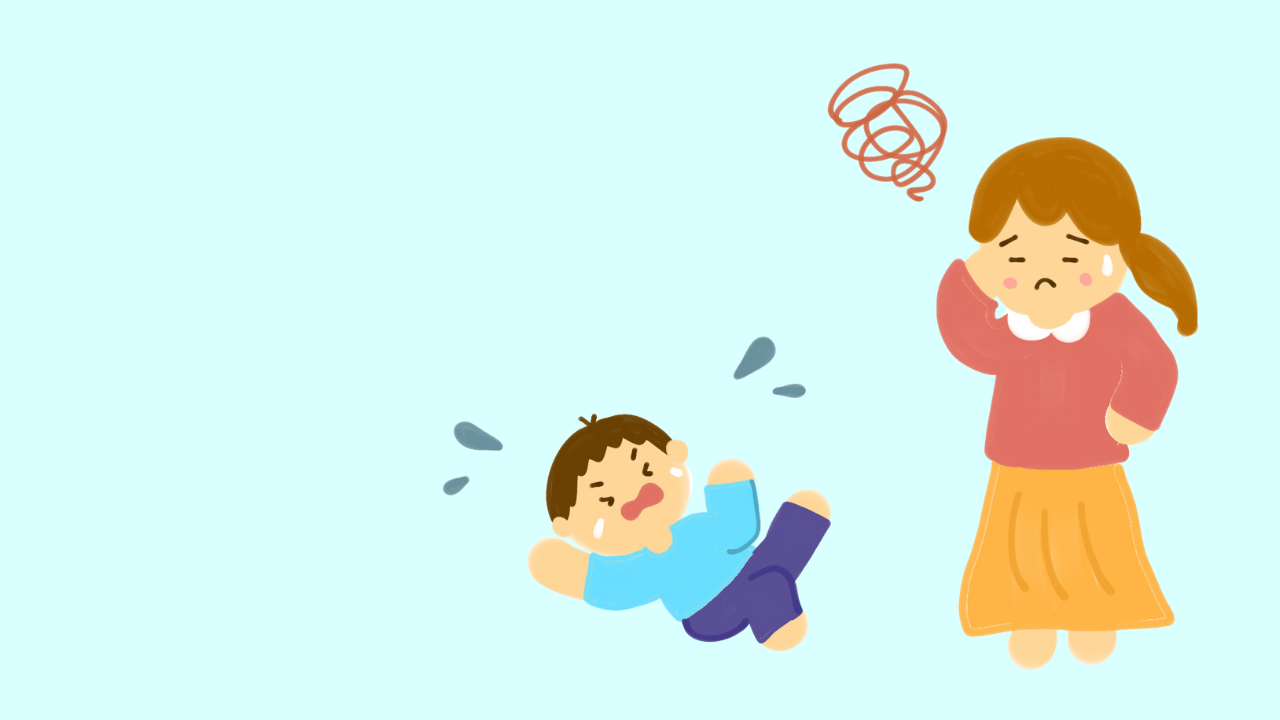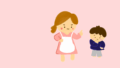子どもの癇癪と発達障害~元精神科ナースが語る理解と対応のポイント~

こんにちは。高校2年、中学3年の発達障害の男の子ママのひまわりです。
精神科ナースとして長年勤務し、現在は発達障害児の子育て経験を活かして子育てコーチングの講師をさせていただいています。
今日は、多くの保護者の方からご相談をいただく「子どもの癇癪と発達障害との関係」について、専門的な視点と母親としての実体験を交えてお話しさせていただきます。
癇癪とは何か?発達障害児の癇癪の特徴
まず、癇癪について正しく理解することから始めましょう。
癇癪とは、感情のコントロールがうまくいかない時に起こる激しい感情の爆発です。泣き叫ぶ、暴れる、物を投げる、自分や他人を叩くなどの行動として現れます。
定型発達の子どもも癇癪を起こしますが、発達障害のあるお子さんの癇癪には以下のような特徴があります
- 持続時間が長い
定型発達の子どもの癇癪が数分~10分程度で収まることが多いのに対し、発達障害のあるお子さんの癇癪は30分以上続くことも珍しくありません。 - 強度が激しい
感情の波が非常に大きく、周囲が驚くほど激しい反応を示すことがあります。 - 予測が困難
一見些細なことがきっかけで始まることが多く、保護者にとって予測が困難です。 - 年齢に比して頻度が多い
同年代の子どもと比較して、癇癪の頻度が明らかに多い傾向があります。毎日癇癪が起きる子もいるくらい頻度は多いです。
発達障害と癇癪の関係性
精神科ナースとして多くの発達障害のお子さんとその家族に関わってきた経験から、癇癪と発達障害には密接な関係があることを実感しています。
①ADHD(注意欠陥多動性障害)と癇癪
ADHDの特性である衝動性と感情調節の困難さが癇癪につながりやすくなります。
主な要因:
・感情のブレーキが効きにくい
・刺激に対して過敏に反応する
・欲求の我慢が苦手
・注意の切り替えが困難
私の息子もADHDの診断を受けていますが、小さい頃は思い通りにならないことがあると、まるでスイッチが入ったように激しく泣き叫んだり、物を投げたり、人を叩くこともよくありました。当時は「なぜこんなに激しく怒るのだろう」と戸惑うばかりでした。
②ASD(自閉スペクトラム症)と癇癪
ASDの特性である感覚過敏やこだわり、変化への適応困難が癇癪の引き金となることが多くあります。
主な要因:
・感覚過敏による不快感
・予定変更や環境変化への拒否反応
・コミュニケーションの困難さによるフラストレーション
・こだわりを邪魔されることへの強い抵抗
③知的障害と癇癪
言語理解や表現の困難さから、自分の気持ちを適切に伝えられないもどかしさが癇癪として現れることがあります。
【癇癪が起こるメカニズム】
精神科での臨床経験を通して、癇癪が起こるメカニズムを以下のように理解しています:
①蓄積段階
日常生活の中で小さなストレスや刺激が蓄積されていきます。発達障害のあるお子さんは、定型発達の子どもよりも多くの刺激をストレスとして感じる傾向があります。
②引き金段階
何らかのきっかけ(断られる、予定が変わる、感覚的な不快感など)で、蓄積されたストレスが一気に爆発します。
③爆発段階
感情のコントロールが完全に効かなくなり、癇癪として現れます。この段階では、理性的な説得は効果がありません。
④消耗段階
エネルギーを使い果たし、疲れ切って落ち着きを取り戻します。
癇癪への適切な対応方法
癇癪中の対応
①安全確保を最優先に
お子さんや周囲の人が怪我をしないよう、危険な物を遠ざけ、安全な環境を作ります。
②冷静さを保つ
保護者が感情的になると、お子さんの興奮はさらに高まります。深呼吸をして、自分自身を落ち着かせることが大切です。
③無理に止めようとしない
癇癪中は理性的な判断ができない状態です。「やめなさい」「静かにして」などの言葉かけは逆効果になることが多いです。
④そばにいて見守る
お子さんが一人ではないことを伝えるため、近くで見守ります。ただし、刺激を与えないよう距離を保つことも重要です。
癇癪予防のための日常的な対応
①環境調整
・感覚過敏への配慮(音、光、触感など)
・予定の可視化(スケジュール表の活用)
・刺激の少ない落ち着ける空間の確保
②コミュニケーションの工夫
・簡潔で分かりやすい言葉での説明
・視覚的な支援(絵カード、ジェスチャーなど)
・感情を表現する言葉を教える
③規則正しい生活リズム
・十分な睡眠時間の確保
・バランスの取れた食事
・適度な運動
専門機関との連携の重要性
精神科ナースとしての経験から、早期の専門機関との連携をお勧めします。
相談できる専門機関
・発達支援センター
・小児精神科
・臨床心理士
・作業療法士
・言語聴覚士
【専門機関でできること】
・正確な診断と評価
・個別支援計画の作成
・療育プログラムの提供
・薬物療法の検討(必要に応じて)
・家族支援とカウンセリング ほか
保護者の心のケア
癇癪への対応は、保護者にとって大きな負担となります。私自身も息子の激しい癇癪に心が折れそうになった経験が何度もあります。
【大切なポイント】
・完璧を求めすぎない
・一人で抱え込まない
・同じような経験をしている保護者とのつながりを大切にする
・自分自身の時間も確保する
・小さな成長も見逃さずに評価する
子どもの癇癪と発達障害との関係まとめ
理解と愛情で向き合う
子どもの癇癪は、発達障害の特性からくる自然な反応であり、お子さん自身もコントロールに苦しんでいます。
重要なのは、癇癪を「わがまま」や「しつけの問題」と捉えるのではなく、お子さんが抱えている困難さのサインとして理解することです。
適切な理解と対応により、癇癪は必ず改善していきます。我が家でも、息子の特性を理解し、環境を整え、適切なサポートを受けることで、癇癪の頻度と強度は大幅に減少しました。
一人で悩まず、専門機関や同じような経験をしている家族とつながりながら、お子さんの成長を支えていきましょう。お子さんの持つ素晴らしい可能性を信じて、一歩ずつ前進していくことが大切です。
発達障害があってもなくても、すべての子どもは愛されるべき存在です。その子らしさを大切にしながら、適切なサポートを提供していくことが、私たち大人の役割だと考えています。