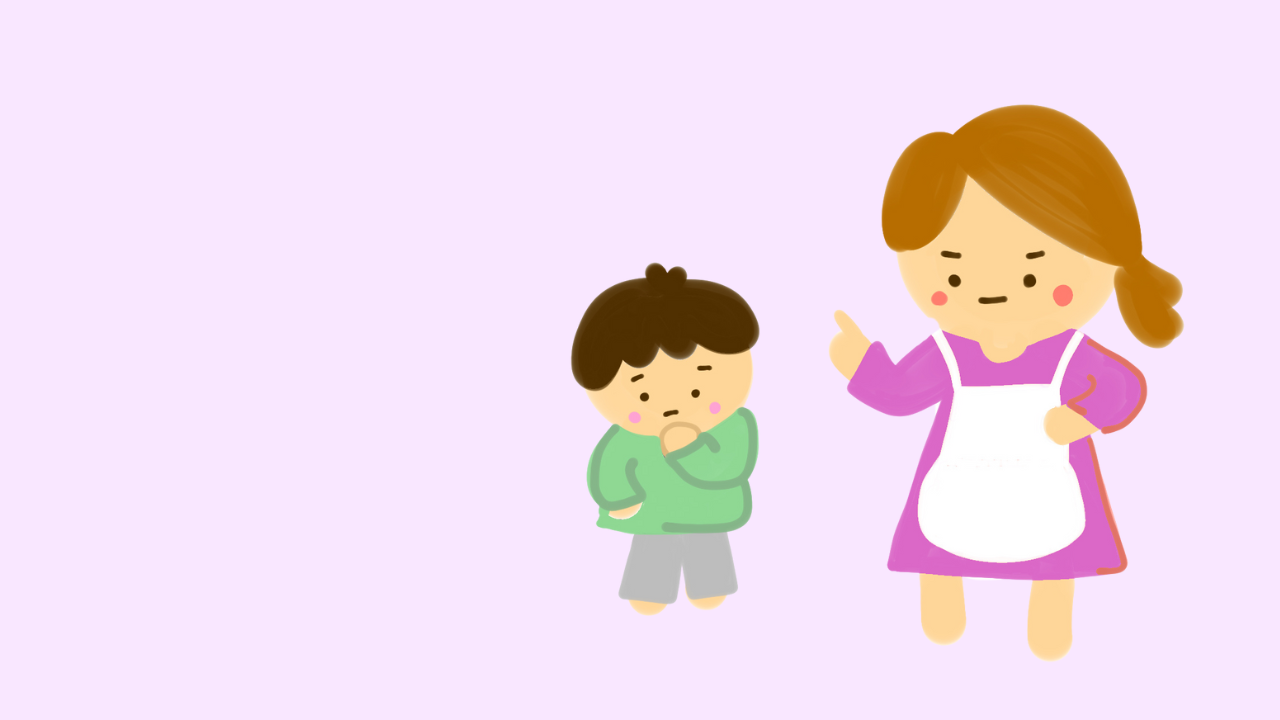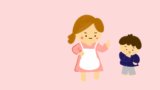我が子を自ら考えて動ける人に育てる方法とは?
こんにちは。高校2年、中学3年の発達障害の男の子ママのひまわりです。
精神科ナースとして長年勤務し、現在は発達障害児の子育て経験を活かして子育てコーチングの講師をさせていただいています。
「指示がないと動けない」「言われたことしかしない」そんな大人が増えていると言われています。実は、指示待ち人間は幼少期からの関わり方で作られてしまうのです。
今回は、指示待ち人間になりやすい子の特徴と、そうならないための具体的な対策をお伝えします。
指示待ち人間になりやすい子の特徴
- 常に親の顔色を伺っている
どんな様子?
・何かをする前に必ず親の許可を求める
・「これでいい?」「合ってる?」が口癖
・親がいないと不安で動けない
・自分の意見を言わず、親の反応を見てから答える
精神科での臨床経験から、このタイプの子どもは過度に親の期待に応えようとして、自分の意思を抑え込んでいることが多いと感じています。ちなみに大人になっても変わらない子も多く仕事に支障をきたすこともあります。
- 失敗を極端に恐れる
どんな様子?
・新しいことにチャレンジしたがらない
・完璧にできる自信がないと始めない
・少しでも間違えると大きく落ち込む
・「できない」「無理」が口癖
失敗体験を責められた経験から、「失敗=悪いこと」と学習してしまっています。
- 自分で選択する経験が少ない
どんな様子?
・「どっちがいい?」と聞かれても答えられない
・優柔不断で決断に時間がかかる
・選んだ後も「これで良かったのかな」と不安がる
・親や友達の意見にすぐ流される
日常的に選択する機会が少なく、決断する力が育っていない状態です。
- 質問や疑問を口にしない
どんな様子?
・分からないことがあっても黙っている
・「なぜ?」「どうして?」と聞かない
・指示をそのまま受け入れ、理由を考えない
・困っていても助けを求められない
好奇心や探求心が抑制されている、または表現する方法を知らない可能性があります。
- 親からの指示が習慣化している
どんな様子?
・朝起きてから夜寝るまで、すべて親の指示で動く
・「次は何するの?」と常に聞く
・時間割や持ち物の準備も親任せ
・自分のスケジュールを把握していない
最も典型的な指示待ち人間予備軍の特徴です。
- 受け身の姿勢が定着している
どんな様子?
・「やりたいこと」より「やらされること」が多い
・自分から「○○したい」と言わない
・暇な時間を持て余す(自分で遊びを見つけられない)
・習い事も親が決めたものばかり
主体性が育つ機会が少なく、受動的な姿勢が習慣になっています。
【なぜ指示待ち人間になってしまうのか?】
親の関わり方が最大の原因
精神科ナースとして、また子育てコーチングの講師として多くの家庭を見てきましたが、指示待ち人間を作る親には共通のパターンがあります。
- 先回りして指示を出す
子どもが考える前に「○○しなさい」と指示してしまう。 - 失敗させない育児
転ばぬ先の杖で、失敗から学ぶ機会を奪ってしまう。 - 完璧主義
「きちんと」「ちゃんと」を求めすぎて、子どもの試行錯誤を許さない。 - 比較や評価が多い
「○○ちゃんはできるのに」「100点じゃないとダメ」など、常に評価される環境。 - 時間に追われた声かけ
「早く!」「急いで!」が口癖で、子どもが考える時間を与えない。
私自身もシングルになってからは時間の余裕が無さすぎて「早く着替えなさい」「早く食べなさい」と指示ばかりしていました。その結果、息子は何をするにも「次は?」と聞くようになってしまったのです。
指示待ち人間にしないための具体的対策
対策1:選択させる習慣を作る
年齢別アプローチ
幼児期(3〜6歳):2択から始める
・「赤い服とピンクの服、どっち着る?」
・「公園と図書館、どっち行く?」
・「りんごとバナナ、どっち食べる?」
小学校低学年(6〜9歳):3択に増やす
・「宿題、お風呂、ご飯、どの順番でやる?」
・「習い事、サッカー、ピアノ、プログラミング、どれに興味ある?」
小学校高学年以上(9歳〜):自由な選択へ
・「今週末、何したい?」
・「夏休みの自由研究、何について調べる?」
重要なのは、選んだ結果を尊重すること。親の望む答えを誘導するのは逆効果です。
対策2:失敗を学びの機会にする
× NG対応
「だから言ったでしょ!」
「お母さんの言う通りにしないから」
「もう自分でやらせない」
○ OK対応
「うまくいかなかったね。何が原因だと思う?」
「次はどうしたらいいかな?」
「失敗から学べたことは何?」
我が家では、息子が忘れ物をした時、責めるのではなく「次はどうしたら忘れないかな?」と一緒に対策を考えるようにしています。その結果、息子は自分で前の日に準備する事を覚えました。それでも忘れた時はホワイトボードに書く事を自分で考え取り入れてます。
対策3:「指示」を「質問」に変える
具体的な言い換え例
指示 ▶質問
早く起きなさい ▶何時に起きる予定?
宿題やりなさい ▶宿題、何時からやる?
片付けなさい ▶どこから片付け始める?
勉強しなさい ▶今日は何の勉強する?
お風呂入りなさい▶何時になったらお風呂入る?
これは私が今でも子どもに声をかける時にやっている『?』をつけて声かけ方です。質問形式にすることで、子どもは自分で考えて答えを出す習慣がつきます。
対策4:待つ力を親が身につける
子どもが考えている時、すぐに答えを出さずに『待つ』ことが重要です。
待つ時のポイント:
・最低10秒は黙って待つ
・焦らせない、急かさない
・考えている様子を見守る
・沈黙を恐れない
最初は時間がかかりますが、徐々に考えるスピードは上がっていきます。
対策5:段階的に自立させる
年齢別の自立目標
幼児期:
・自分で服を選ぶ
・自分でおもちゃを片付ける
・自分で靴を履く
小学校低学年:
・自分で時間割を揃える
・自分で宿題の計画を立てる
・自分で朝の準備をする
小学校高学年:
・自分で1日のスケジュールを管理する
・自分で習い事を選ぶ
・自分でお小遣いを管理する
中学生以上:
・自分で進路を考える
・自分で問題解決する
・自分で生活リズムを整える
・自分の朝ごはんを用意する
対策6:「なぜ?」を大切にする
子どもの「なぜ?」「どうして?」という質問は、思考力を育てる絶好のチャンスです。
× NG対応
「そういうものだから」
「理由なんてない」
「うるさい、黙ってやりなさい」
「今忙しい」
○ OK対応
「なんでだと思う?」(逆質問で考えさせる)
「一緒に調べてみよう」
「お母さんはこう思うんだけど、あなたはどう思う?」
対策7:成功体験を積み重ねる
自分で決めて、自分で行動して、うまくいった経験が自信になります。
小さな成功を認める
・「自分で決めたんだね」
・「自分で考えて行動できたね」
・「自分の力でやり遂げたね」
結果ではなく、「自分で決めて行動したこと」自体を褒めることが重要です。
対策8:環境を整える
考える時間を確保する
・朝は余裕を持って起きる
・スケジュールに余白を作る
・せかせかしない生活リズム
情報を可視化する
・カレンダーで予定を見える化
・やることリストを一緒に作る
・選択肢を視覚的に示す
【発達障害児への特別な配慮】
発達障害のあるお子さんの場合、定型発達の子どもより丁寧なサポートが必要です。
ADHDの場合:
・選択肢は2〜3個に絞る
・視覚的なサポート(絵カード、チェックリストなど)
・短時間で達成できる目標設定
ASDの場合:
・選択肢を明確に示す
・予測可能な環境を作る
・パターン化して安心感を与える
我が家の息子たちも発達障害がありますが、それぞれの特性に合わせたサポートをすることで、少しずつ自分で考えて動けるようになってきました。
まとめ:指示待ち人間にしないために
指示待ち人間にしないためには、今日から以下のことを始めてみてください
- 1日1回は子どもに選択させる
「○○しなさい」を「いつ○○する?」に変える - 失敗を責めず、次への対策を一緒に考える
- 子どもの答えを10秒待つ
- 小さな自己決定を認めて褒める
完璧を目指す必要はありません。少しずつ、親の意識を変えていくことが大切です。
子どもの可能性を信じて、「待つ」「任せる」「見守る」勇気を持ちましょう。
将来、社会に出た時に自分で考えて動ける人になるための土台は、今日の関わり方から始まっています。

一緒に頑張りましょう!